典型的な父と息子の葛藤後に賢治は日蓮宗の熱心な信徒になったが、父親は浄土真宗の熱心な門徒で、花巻仏教会を組織するのに尽力したような人だった。賢治はその父親を日蓮宗に改宗させようとして失敗してからは、親子関係が険悪になった(しかし、賢治は父からの経済的援助は完全に拒絶する気にはなれなかったようで、そのお金のおかげで旅行したり、勉学や布教活動が続けられたこともある)。だが、死ぬまで続いた親子の不和の主因は信じる宗教の教義の問題ではなく、父と息子によくある根本的な性格の不一致から生じる衝突といえるようだ。どちらも相手をありのままに受け入れようとはしなかった。父親は狭量な家長で、貧乏人から質草を取って金を貸すのを生業とし、息子もまた度量が狭いが信念を貫く反逆児で、人々の幸福のためなら迷うことなく自己を犠牲にする決意をしていた。父と息子はこの生来の性格の不一致のせいでかえって深く結びついていた。賢治の病も二人の絆を強くしたようだ。中学生のとき賢治は盛岡の岩手病院で鼻の手術を受けた。息子を見舞った父親はその後髪の毛が抜け始めた。手術後に賢治がかかった感染症が父親にも伝染したようだ。もっと迷信の深い時代だったらば、不幸でみじめな病人の気持ちを多少でも父親に理解してほしいという賢治の願いが通じたのだと考える人がいてもおかしくないだろう。 1905年に日露戦争で勝利をおさめた日本では国全体が愛国主義に燃えていた。日本は朝鮮半島を植民地にする準備を着々と進め、1910年に武力で日韓併合を成し遂げた。使命感に燃える優秀な若者たちの多くは−−賢治の心にもたえず使命感が燃えていた−−自己の才能と愛国心を発揮する場としておもに貿易業か軍隊のいずれかを選んでいた。しかし、賢治は進学するにつれて植物と岩石に強い関心を抱くようになる。もし彼が東京か京都に生まれていたら、大学に進んで立派な自然科学か生物学か地質学の研究者になっていただろう。実際には賢治は農耕学を選んだが、知的娯楽として生物学や地質学の研究も続け、後には天文学も学んだ。 事実、賢治は一流の好事家で、語学、とくに英語、ドイツ語、エスペラントを熱心に学び、クラシック音楽をこよなく愛したが、彼が自らチェロもやり、蓄音機(グラモフォン)でかけた音楽は、当惑しながら頬を赤くほてらして聞いていた若い聞き手たちにはさぞうんざりするものだっただろう(賢治は自分で作った竹針でレコードをかけていたこともあった)。 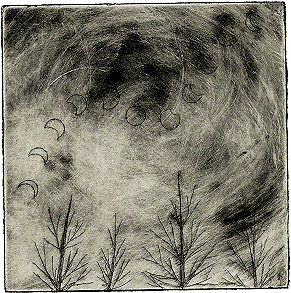
花巻の野原のそばに立つ家で始めた羅須地人協会での賢治の指導者ぶりを紹介しよう。生徒の前を行ったり来たりしながら、エスペラントを創案した眼科医のユダヤ系ポーランド人ルードヴィック・L・ザメンホフの才能について、生徒の耳にたたき込もうとばかりに講義したり、バナナン大将とかいう英雄を主人公にした劇『飢餓陣営』などの稽古をさせたり、生徒のなかには、ときたまでもイワシの干物が膳にのればわくわくして眺めるような青年たちもまじっていた時代に、菜食主義の喜びをとくとくと説教したりしていた。 親が運ばせた食事を拒絶し、これみよがしに井戸に捨てたという話や友達を横にすわらせて山のようなトマトを無理やり食べさせたという、賢治にまつわる逸話は事実だったのだろう。賢治にとって食べるという行為さえもエゴのなせる業と思えるようになった。ロシアの作家ニコライ・ゴーゴリと同様、賢治の人生の唯一の目的、および作品を生む霊感の源は宗教への狂信になった。さらに、ゴーゴリと同様、賢治の死も断食死だとも言えるかも知れない、少なくとも彼は自ら結核を悪化させ進行させたと言えるだろう。 従って賢治の人生には二つの重要なテーマがあり、両方とも罪の意識に関連していた。一つは父親のひざもとで植えつけられた罪悪感、もう一つは人に教えたいという内的欲求からくるものだった。両者があいまって自己犠牲という観念を生み出し、それが結果的に賢治の肉体をむしばんだことになるのだが、その一方で精神的遺産を生み残していて、半世紀以上たってやっとそこに光が当てられるようになったのである。 |

